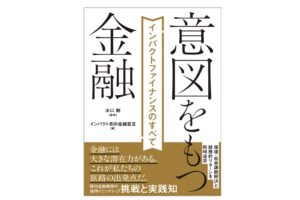定常社会を提言する広井良典氏は、人口減少社会のデザインの中で『日本全体の持続可能性を図っていく上で、「都市集中」-とりわけその象徴である一極集中―か「地方分散」かという分岐ないし対立軸が、もっとも本質的な分岐点ないし選択肢である』と述べています。私は、「撤退なのか、むらおさめなのか、農村たたみ反対なのか」という対立を起点に日本全体で選択肢をさらに深く議論すべきと問題提起してきました。 農水省は中山間地域等直接支払制度の集落機能強化加算の廃止に向け動いています。集落運営組織が行っている高齢者の見守りや交流サロン、買い物支援などへの支援が打ち切られます。このままなし崩し的に生命線のおカネを断ち切り続けると農村は突然死しかねません。農水省は農村の撤退に動き始めているのでしょうか。今までの議論の推移をまとめてみました。みなさまのご意見をお待ちします(斉藤俊幸)。

中山間地域等直接支払いとは何か
中山間地域等直接支払制度は、日本の農業政策の一環として、特に農業生産条件が不利な中山間地域において、農業の維持と多面的機能の確保を目的とした制度です。この制度は、2000年に導入され、農業者が5年以上にわたり農業生産活動を継続することを条件に、交付金を支給する仕組みです。中山間地域は、地形や気候条件が厳しく、農業生産が困難な地域です。これらの地域では、過疎化や高齢化が進行しており、耕作放棄地の増加が懸念されています。このため、農業の持つ多面的機能(例えば、水源の保全や土壌の浸食防止など)を維持するために、国と地方自治体が支援を行ってきました。中山間地域等直接支払制度の対象となる地域は、特定農山村法や山村振興法、過疎法に基づいて指定された地域です。
雑草刈りも中山間地域等直接支払制度の対象
雑草刈りは、中山間地域等直接支払制度の対象となる活動の一部です。この制度は、農業生産条件が不利な中山間地域において、農業生産活動を維持し、耕作放棄を防止するために設けられています。対象となる活動としては雑草刈りを含む農業生産活動の維持、水路や農道の管理、周辺林地の管理などです。

農水省による中山間地域等直接支払いの集落機能強化加算の廃止
農水省は、2025年度の予算概算要求において「中山間地域等直接支払交付金」の一部である「集落機能強化加算」を廃止する方針を示しました。この加算は、農村地域の生活支援や地域活動の維持に重要な役割を果たしてきたため、廃止に対する反発が強まっています。「集落機能強化加算」は、2020年度から2024年度までの第5期対策に新設されたもので、地域の生活支援や営農以外の活動を支援するために設けられました。この加算は、過疎化や高齢化が進む中山間地域において、地域の小売店舗の経営や配食サービス、送迎支援など多様な活動を支えるために利用されてきました。廃止が決定されたことに対し、地域住民や専門家からは「店舗を継続できない」「病院への送迎支援に欠かせない」といった懸念の声が上がっています。

集落機能強化加算の廃止で地域運営組織は大きな影響を受ける
集落機能強化加算の廃止は、地域運営組織(RMO)に深刻な影響を及ぼすと考えられています。この加算は、農村地域の生活支援や地域活動の維持に重要な役割を果たしてきました。第一に生活支援の減少が考えられます。 集落機能強化加算は、過疎化が進む農山村において、店舗の運営や交通支援、配食サービスなど多様な地域活動を支えるために利用されてきました。この加算が廃止されることで、これらのサービスの継続が困難になると懸念されています。また、地域運営組織の機能低下が考えられます。 RMOは、地域の自立した運営を目指す組織であり、集落機能強化加算を活用して地域の課題解決に取り組んできました。加算の廃止により、これまでの活動が支えられなくなり、地域の運営能力が低下する可能性があります。

集落機能強化加算の廃止に関する反対意見
中山間地域等直接支払制度の集落機能強化加算の廃止に関する反対意見は、主に地域の農業の持続可能性やコミュニティの活性化に対する懸念から生じています。中山間地域は高齢化や人口流出が進んでおり、農業の継続が困難になっています。直接支払い制度の集落機能強化加算の廃止は農業の衰退を加速させる恐れがあります。この制度は、集落単位での取り組みを促進し、地域の結束を強める役割を果たしています。廃止により、中山間地域の農村は撤退を余儀なくされるのではと考えられます。
農水省中山間地域等直接支払いの第三者委員会の最終取りまとめが紛糾
12 回中山間地域等直接支払制度に関する第三者委員会は、令和7年3月 31 日(月)(書面提出による持ち回り審議)に開催され、第5期対策最終評価の修正案に対し、一部の委員から反対意見があったため、取りまとめには至らなかったと農水省は明記しています。委員の意見も開示されています。https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_daisan_5ki/attach/pdf/12-2.pdf
橋口卓也委員の意見(抜粋)
生活支援に使える加算措置を廃止
このままの修正案としての取りまとめに反対します。具体的には、大きく、以下の2つの点の修正が必要であると考えます。「集落機能強化加算をネットワーク化加算に見直したが、」との表現がありますが、本質は、生活支援に使える加算措置を無くすということであり、このままの表現では、第 11 回委員会を開催するに至った背景、あるいは第 11 回委員会の議論の重要点が伝わらないものと考えます。よって、「集落機能強化加算を廃止し、ネットワーク化加算を新設したが、」との表現か、あるいは「生活支援に使える加算措置である集落機能強化加算をネットワーク化加算に見直したが、」という表現を使っていただくようお願いいたします。提示された最終評価の修正案は、事務局からの集落機能強化加算廃止の必要性の説明については、議事録通りにほぼ全面的に展開されている一方、委員側の意見が断片にしか掲載されておらず、「議事概要」としては、ふさわしくないものと考えます。よって、以下のように追記していただくようお願いいたします(以下は、既に記載済みのものも含む)。なお、各委員の発言の数や発言時間などは異なっていたので、仮に各委員当たりの発言数を統一するということならば、この点も「議事概要」としては、ふさわしくないものと考えます。
委員側の意見が断片にしか掲載されておらず「議事概要」としてふさわしくない
第三者委員会は、最終評価に至る議論を大事にしていたが、集落機能強化加算にマイナスの要素はなかった中で、廃止は突然示されたものであり、委員会を軽視するものとして遺憾。真摯に活動に取り組まれてきた現場の皆さんにも与えた影響は非常に大きいし、不安も各方面に広がった。現行基本計画の中でもEBPMの推進を打ち出しており、農水省全体としての政策立案の在り方に対して、齟齬をきたすものではないか。最終評価には、集落機能加算について否定的な評価は全くない。集落機能強化加算の取組比率が低いというが、集落協定広域化加算の取組面積の方が集落機能強化加算の半分もなく、集落機能強化加算を廃止しようとする意図がよく分からない。集落機能強化加算の進め方に課題があったのであれば、問題点を直せば有効にできるのではないか。
予算概算決定には地域運営組織という言葉も出てこない
集落機能強化加算は、集落機能が低下してきた集落の下支えの部分を下支えするという趣旨と捉えることができるのではないか。短期間で小規模な集落が一挙にネットワークを広げて、RMO相当までいくというのはなかなか難しいだろう。4期対策の最後の集落機能強化型のときには、割と明示的に地域運営組織が出てくるが、5期対策の予算概算決定には、地域運営組織という言葉も出てこない。必ずしも地域運営組織ができることがなくても、あるいは連携がなくても集落機能強化につながるということはあり得るのではないか。
高齢者の見守りや交流サロンの取組が不十分だったから廃止するというのは手のひら返し
農水省で出している事例集でも、集落機能強化加算を生かした活動として、高齢者の見守りや交流サロンの開設などが紹介されており、直接的には関係ないように見えるけれども、農地の保全を図ることができると紹介されている。見守り活動とか、種々のレベルの活動を一旦は評価しておきながら、あなた方の取組が不十分だったから廃止するというのは、手のひら返しではないか。説明が不十分だった理想像に至ったところが少ないので、廃止するといったことでは、現場は何を信じて活動すればいいのか。生活の安心感が営農、地域保全、農地保全というのに深く結びついているし、途中までは農水省もそういう事例でも評価していた。モデルの活動から学ぶべきところは多いけれども、いろいろな活動を評価していただきたい。違反ではないから加算の返還ではないけれども、不十分な不十分な活動だということで大変厳しい評価をしている。第 11 回委員会の資料は廃止することの正当性を強調するあまり、過度に厳しい評価になっている。集落機能強化加算という名称が機能を強化するということなので、必ずしも体制づくりとか体制整備をもともと意味していない名称になっていた。本来であれば加算措置を全てをきちんと俎上にのせて、議論をするということがもっと前にあるべきだった。特に集落機能強化加算に当てはまる特徴といえないのであれば、中立性の観点から、加算措置全てに対して議論をし、評価すべき。集落機能強化加算による取組が必ずしも協定組織の強化や農業生産活動の継続につながらなかったというデータがないと評価としてふさわしくない。評価に当たっては客観的なデータを用いることが大前提で、EBPMの流れでもそうだと思うが、一方的に評価を書いてしまうとそれは根拠がない。
集落を支えることが農村、農地を維持することに必要という共通認識が大きく方向転換
基本的には個々の協定組織に対して伴走支援が必要であるが、自治体の担当者は手一杯の状況で、しっかりとした推進体制の構築が必要である。集落機能強化加算そのものの考え方が適切でないという説明がなく、説明と内容が一致してないのではないか。集落機能強化のプロセスは多様であり、集落機能強化加算の評価軸をどう取るか熟議しないといけない。特に中山間地域では、営農と生活の一体性というのもあり、農地の保全につながっているという関係性はあり、集落戦略では生活コミュニティの維持が生活面で不安がないかということも問うていた。集落をしっかり支えることが、農村、農地を維持することに必要という共通認識が大きく方向転換されるとすれば、そのための議論をすべきである。