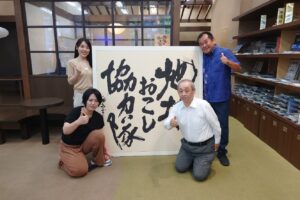永松俊雄氏
不明なリスク
2016年4月14日、16日に熊本地方で発生した震度7(M6.5、7.3)の地震は、各地に大きな被害をもたらした。熊本県内だけで885ヶ所に18万人以上の住民が避難した。内閣府の推計では、被害総額は最大で4兆6千億円に及ぶ。政府の地震調査研究推進本部によれば、今後30年間に国内で発生すると思われる大地震の発生確率は、関東地方が50〜60%、東海地方が70%である。一方、本震の震源とされる布田川断層帯(布田川区間)では、30 年以内にM7.0 程度の地震が発生する確率は、ほぼ 0%~0.9%と推定されていた。熊本地方は、これまで大地震の発生確率が最も低い地域の1つに分類されていたのである。これは、私たちの自然に関する知識がいかに乏しいかという、明らかな証拠でもある。阪神・淡路大震災も、直前の予測では発生確率は0.02~8%だったし、東日本大震災による津波も予想外の出来事だった。「大災害はいつどこでも起こり得る」ことを、熊本地震は改めて私達に知らしめた。

熊本地震(写真提供:永松氏)
情報共助
被災直後、私達にとってまず必要なものは「情報」である。激震で飛び起きても、情報がなければ次の行動が選択できない。しかし、私達個人では情報が入手できない。それを補ったのが、テレビ、ラジオ、インターネットだった。地元の報道各社は、発災直後から被災状況や被災者の声などの情報を流したが、これは住民や自治体職員の行動選択に重要な役割を果たした。マスコミからの(時には自治体にとって耳の痛い)情報提供によって、自治体職員も現状をより正確に把握し、対策を考え、あるいは各所で生じている「不都合」を察知し、改善していくことができたのである。また、TwitterやFacebookなどの情報ツール(SNS)も役立った。発災直後は一部で憶測情報も流れたが、その後ネット上には、道路状況や営業している店舗、銭湯や温泉の開館状況など、住民生活に直結する様々な情報が、かなり正確に書きこまれていった。これは、自治体に代わって必要情報を住民に伝える重要な役割を果たした。福島第一原発事故の際、国はパニックを避けるために、住民だけでなく地元自治体にも放射線物質の飛散情報を伝えなかったが、これは誤った判断だ。なぜなら、行動選択に必要な情報があれば、被災地の人達は思いのほか冷静に意思決定ができることを、今回の地震で被災者が身をもって示したからだ。

熊本地震(写真提供:永松氏)
自治体間共助
自治体職員は、大災害が発生すれば気力、体力の続く限り頑張るものだ。それでも人手は圧倒的に不足する。最も深刻な被害を受けた益城町は、本震翌日、町民の約半数の1万6,050人が避難した。これは、職員1人当たり約97人に当たる。これでは避難所での対応も困難である。人員不足を補う重要な手段の1つが、自治体間の相互協力ネットワークだ。しかし、被災自治体からの要請を待つこれまでのやり方(プル型)では、派遣までにどうしても一定の時間がかかる。報道によれば、熊本県の要請を受けて福岡県が第1陣を派遣したのは、本震4日後だった。派遣を少しでも早めるには、発災後直ちに(被災自治体の要請を待たずに)職員を派遣する「プッシュ(自動発動)型」の仕組みが必要になる。なお、過去の例を見れば、被災1ヶ月を過ぎた頃から、気力・体力の限界から体調を崩す、中には休職・退職に追い込まれる職員も出てくる。1週間、1ヶ月、半年、1年という各局面を見ても、十分な人員が確保されているとは言い難い。被災後の自治体の慢性的な人員不足を解消するには、現在のやり方では不十分である。
熊本地震(写真提供:永松氏)
国・自治体間共助
非常時には、国、自治体ともに通常時とは異なる対応が求められることになる。未経験の事態に直面し、かつ不足する情報のもとでは、うまく事が運ばないことや想定外の出来事がつきものだ。その際の基本原則は、できる限り早く対応し、生じた不具合をその都度修正していくことである。これが、結果として被害やトラブルを最小限に食い止めることになる。例えば国の支援物資は、本震以降、熊本県内の中継拠点に続々と到着したが、受入れ自治体の人員不足から、膨大な支援物資が中継拠点に山積みされ、各避難所への配給が滞った。そこで国は、県の施設を介さない支援物資の運搬方法に変更し、自衛隊や物流業者が直接、市町村や避難所に送る手法に切り替えた。大災害が発生した途端、被災自治体は圧倒的な人員不足に襲われ、各所で手が回らなくなる。従って、平常時の国、自治体の所掌範囲の垣根を越えて、現場の状況に合わせた行政間の共助が、緊急時には求められるのである。

熊本地震(写真提供:永松氏)
社会共助
大災害といっても、地域ごとに被災状況は様々だ。道路が寸断された地域、土砂崩れの危険地域、液状化の地域、多くの家が倒壊の危険がある地域、都市部と中山間地でも事情は異なる。当然ながら、住民同士の共助も、場所によって様々な様相を呈することになる。発災直後、ある地区では、近所同士で倒壊家屋から住民を助け出した。別の地区では、消防団や自治会が安否確認を行い、あるいは地域住民を安全な場所に避難させた。私の自宅周辺では、近所同士で無事を確認した後、手分けして水や食料を確保し、しばらくの間、夜は近くの空き地で共に車で寝泊まりした。避難所に避難した住民の事情も様々だ。健常者だけでなく、1人では屋外の簡易トイレに行けない障害者、要介護者もいれば、妊婦や乳幼児、日本語がわからない外国人もいる。避難所ではプライベートは保てず、女性が着替えをすることも難しい。ペットも連れて入れない。避難所を避け、車中泊を選んだ住民も多数いた。しかし、狭い車内での寝泊まりは、1週間を過ぎると相当の困難が伴う。避難所や車中生活を諦めた住民は、倒壊しそうな家に戻った。自治体が、このような住民一人ひとりの事情を把握することも対応することも、物理的に困難である。自助、共助、公助を、地域事情に合わせて重ね合わせなければ乗り切れないのが、大災害の特徴の1つだ。本震後数日経ってからは、ボランティアによる共助が力を発揮し始めた。避難所での手伝いはもとより、がれきの撤去、散乱した家財の片づけ、炊き出し、テント村の開設、キャンピングカーの無償貸出、外国語の通訳支援、ネット上での支援ニーズとボランティアのマッチングなど、その支援は多岐にわたった。多くの被災者が、彼(彼女)らの献身的な支援に、深く感謝した。「子どもボランティア」の活躍も目立った。避難所にいた小学生達は、トイレ掃除や食事の準備、食料配布の手伝いを買って出た。中高校生らも、高齢者のトイレの手伝い、炊き出しやゴミの回収、新聞配布などを自主的に行った。ボランティアや子ども達の笑顔には、不思議な力が確かにある。阪神・淡路、東日本大震災、広島大水害等の災害を経て、わが国社会には社会共助の精神が着実に根づいていることを、熊本地震は証明することになった。

熊本地震(写真提供:永松氏)
住宅自助と公助
震災後の混乱が一通り落ち着き、以前の生活を取り戻す段階になって、多くの被災者が抱える最大の問題が「住居の確保」である。住宅被害は、熊本県内だけで約14万棟、推計で約10万人が家には住めなくなった。わが家も半壊し、もはや住めない。私がそうしたように、震災後4~5日過ぎてからは、多くの被災者が不動産会社を回っては店先に列をなした。大災害に備えて、水や食料の備蓄、家具の固定、非常用持ち出し袋の用意といった自助は、やろうと思えば可能だ。しかし、将来の自宅損壊に備えて資金を蓄えることは、容易ではない。年金生活者であればなおさらだ。自治体でも、公営住宅の貸出し、仮設住宅、民間の賃貸住宅を「見なし仮設」として認める(いずれも無償)等の措置を取っている。しかし期間は最長2年間であり、文字どおり「仮の住まい」である。この制度は、大半の世帯に働き盛りの大黒柱がいる一昔前の社会を前提にしたものだ。「その後は自助で」という発想は、高齢化が進んだ現代にはそぐわない。「終の棲家」を確保できない高齢者や母子世帯を視野に入れた、新たな住宅公助を検討する時期に来ている。

熊本地震(写真提供:永松氏)
企業の社会的使命
大災害時、住民の生命や生活(衣食住)に直接関わる業界には、強い「公共性」が求められる。例えば、セブンイレブンは、発災後も大半の店舗が営業を続けたが、おにぎりやパンは入荷するとすぐに売り切れた。ホームセンターには、屋根を覆うブルーシートを買う住民が列をなした。おにぎりやブルーシートの価格を2倍、3倍にしても、被災者は買ったであろう。しかし、小売業者はそのようなことはしなかった。あるいは、複数の企業が飲料水や食料、毛布などを被災者に無償で提供した。損害保険会社は、今回の地震で多額の保険金を支払うことになったが、複数の会社の調査員が、本社から「できる限り被災者の方々に配慮せよ」との指示を受けていると語っていた。これが、緊急時に求められる企業の社会共助の1つのあり方だ。熊本地震では、小売業だけでなく医療、エネルギー、流通、情報通信、保険といった多くの業界が、(損得は別にして)企業の社会的責任を果たそうと努力した。建設業界はどうであろうか。東日本大震災時の応急仮設住宅(9坪)の建設単価は、宮城県で約730万円(坪約81万円)、撤去費用を含めれば約850 万円(同約94万円)である。人手不足、品不足が価格高騰の理由なのだが、驚くべきことに、これは建築コストが最も高い住宅メーカーの平均単価(坪約85万円)よりも高いのである。坪80万円出せば、RC(鉄筋コンクリート)の住宅を建てることもできる。これまで建設業界は、災害を「特需」と捉えてきた。事実、東日本大震災という特需を受けて、大手建設各社はバブル期以来の好決算を続け、「わが世の春」を享受している。さて、住宅着工統計(2015年)によれば、熊本県の戸建住宅の平均工事費予定額は1,913万円である。仮に、仮設住宅の建設・撤去費用(宮城県の場合1戸850万円)を、被災者支援に回したとしよう。新築の場合には、費用の半分近くが補てんされる。補修で済む半壊家屋であれば、それだけで費用の大半が賄える。もし地震保険(火災保険1,800万円、地震保険900万円)に入っていれば、全壊なら100%保険金が支払われるので、新築費用の大半を賄える。半壊補修の場合には、保険金(同450万円)の多くがそのまま手元に残ることになる。自治体にしても、仮設住宅の建設・撤去費用で、住民の住まいが確保できるのであれば、2年後に解体する仮設住宅を、あえて建設する理由はない。住居問題については、被災者の自助、企業の社会共助、そして公助のあり方に関して、正面から議論すべき時期に来ている。
大災害は、いつどこで起こるかわからない。しかし、非常時にこそ、個人、団体、企業には社会の構成員としての「互恵的協働」が求められるのであり、その行動の積み重ねが、被災地だけでなく、ひいてはわが国を守り、支えていくことになるのである。

熊本地震(写真提供:永松氏)