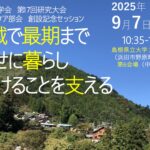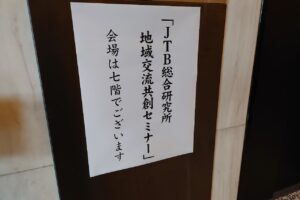10年ぶりの只見町訪問
只見町教育委員会から2015年8月に只見高校の存続へ向けた講演に呼ばれ、卒業生の都会への流出を防ぐためには魅力ある農業の雇用創出が必要であると話しました。講演後にお会いした地元の農家の若者に米焼酎製造という方法があることを紹介し、特産しょうちゅう製造免許の存在とすでに同免許で米焼酎を製造している高知県本山町の紹介と中古設備を使った設備工事会社を紹介しました。あれから10年、彼らは飛躍的な成長を遂げ、全国でも知られる存在になりました。そしてこれから新たなイノベーションを仕込もうとしています。


ばうむ合同会社(高知県本山町)視察訪問(2016年3月)
米焼酎を製造する合同会社ねっかが総務省のローカル10000プロジェクトを活用してウィスキー事業に進出
福島県奥会地方は最も遠隔にある地域です。東北新幹線新白河駅を下車して自動車で山道を超え2時間はかかります。東武線特急で浅草駅を出発して終点まで3時間を要し、その終点の会津田島駅から自動車でさらに1時間はかかります。上越新幹線浦佐駅から自動車で向かうと会越六十里という難所を3時間上り続け奥会津地方にあるダムに到達します。しかし合同会社ねっかはそのダムの向こうにある福島県の最深部、只見町にあります。同社は総務省のローカル10000プロジェクトを活用し、ウィスキー事業への進出を決めました。この状況を把握するために総務省地域力創造グループが視察を行うことになり、ねっかの起業支援を担当した私も同行することとなったのです(斉藤俊幸)。
2016年に農家が酒造会社を起業、日本酒蔵従業員を社長として招聘、彼らが維持する水田は約300ヘクタール
福島県只見町の合同会社ねっかは2016年に当時30~40代の農家4名が日本酒の製造会社に勤める人を社長に招聘して起業した米焼酎会社です。起業から9年を迎え、雇用は5名となっています。同社に並行して特定地域づくり事業協同組合を作り、農家の従業員は春から秋にかけて農業に従事し、冬は酒造会社への派遣を行うことで地域の通年雇用を実現しています。事業協同組合の雇用は現在8名です。ねっか合同会社の経営に参加する4人の農家と同社が米作りに参加し原料となる酒米を生産しています。彼らが維持する水田は約300ヘクタールです。蒸留所は古民家の作業場を改築して活用しています。樽によるお酒の熟成は蔵で行っています。新しい工場を融資を活用して新設しました。古民家や敷地は同社が購入しました。同社の年商は8000万円を超えます。同社は国内外の酒造コンテストで受賞を重ねているほか、日本農業賞など国の表彰も数多く受賞する注目の企業となりました。ここまですごいぜ!ねっかさすけね!(全然問題ない)

集落存続のカギは地域ビジネスによる連続的なイノベーション
合同会社ねっかは、自著「限界集落の経営学」(学芸出版社)で定義した土地利用型地域ビジネスのモデルとなった会社です。存続危機に直面する集落にあって、農家が会社のリーダーを招聘して起業するとともに、JGAP認証圃場とした農地300ヘクタールを維持し、高付加価値な酒類を製造しています。集落存続のカギは地域ビジネスの勃興であることをねっかが示しています。連続的なイノベーションが大切です。

酒造好適米の五百万石、夢の香を使用
減圧蒸留器を導入
常圧の蒸留器は100度が沸点です。圧力に耐えられる蒸留器を使い、減圧すると沸点が下がます。ねっかはこの特性を活用して沸点30度でもろみを蒸留しています。これにより米焼酎なのに、吟醸香が残った米焼酎を造ることに成功しています。名高い日本酒が多い東北にあって、吟醸香の残る米焼酎は地域の酒として受け入れられているのです。日本酒、焼酎の技術を使った米を原料としたウィスキーづくりを目指しています。ライスウィスキーによる新たな市場開拓が始まろうとしています。

樽で熟成するとライスウィスキーは琥珀色を醸し出す

テイスティングルームで詳しく説明
世界のコンテストで受賞多数



日本農業賞を受賞

首相官邸訪問

小学5年生の酒造り

18歳の酒造り
只見駅前どぶろく

農家は春から秋にかけて農業に従事し、農閑期となる冬は特定地域づくり協同組合を通して酒造会社の従業員として働く。豪雪地帯にありながら雇用の通年化を実現している(右:組合事務所)


ねっか全景