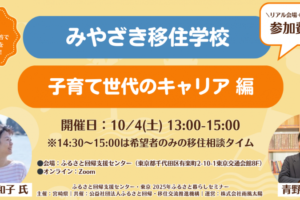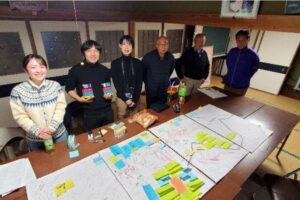知識基盤社会を支える三分野での功績
清成忠男(1933-2024)の残した業績は、大きく、①中小企業・ベンチャービジネス研究、②地域経済研究、③大学改革・高等教育振興の3分野にわたる。この三分野は一見すると、相互にはあまり関連性がないようにもみえるが、実は相互に大きく関係がある。まず、第一の「中小企業・ベンチャービジネス研究」については、清成忠男が「ベンチャービジネス」という和製英語を定義して広めた3人(清成忠男、中村秀一郎、平尾光司)のうちの1人として知られるだけでなく、1999年の小渕内閣での中小企業基本法の抜本改正に際して、中小企業政策審議会基本政策部会会長として携わり、中小企業弱論にもとづく保護政策から、意欲あるベンチャー企業やスタートアップ支援への政策転換をはかった。日本ベンチャー学会を立ち上げて初代会長を務め、産学官連携型の新しい形の学会の在り方を自ら提起した。また、従来から根強く学界に存在していた、大企業と中小企業との「二重構造論」の定説を打ち破ることにつながった。元々、清成忠男は、東京大学経済学部で、大塚久雄門下の高橋幸八郎ゼミに所属しており、比較経済論やドイツ経済史が本来の専門分野である。高校生の頃から研究者を志向しており、大学進学にあたっては、青山高校への通学路で、自宅の庭いじりをしている姿をよく見かけていた大内兵衛(東京大学教授を経て法政大学総長)にも相談をして、経済学部への進学を勧められたという。大学では学部生でありながら1日13時間を図書館で過ごすという、院生のような生活をしていたが、家庭の事情により、大学院への進学をあきらめている。家庭の事情というのは、父親が終戦末期に拓務省(1942年廃止)の官僚を辞任したことが関係していると伺っているが、詳しくは不明である。就職活動の結果、当時の花形企業・東洋紡と政府系金融機関である国民金融公庫(現・日本政策金融公庫)の両方から内定を得たが、ゼミの恩師である高橋幸八郎に相談したところ、「国民金融公庫の方が政府系でヒマだろうから研究時間も取れるだろう」ということで、国民金融公庫に入職している。この選択が、清成忠男の後の研究分野を決定づけている。それは、国民金融公庫新宿支店の融資課で中小企業の現場を回っていると、大学の研究室で議論されているような、必ずしも弱者的な中小企業や、食い詰めて仕方なく起業するという形態ばかりではないことに気が付いたからである。ニッチな分野で独創的な技術、サービスをもって旺盛な事業活動を展開している中小企業、企業家精神旺盛に逞しく事業を行っている中小企業群が存在していることがわかったという。特に、清成忠男が東京大学の授業でも履修していた有澤廣巳(東京大学教授、後に法政大学総長)の持論であった「二重構造論」がどうもあやしい、と現場で気がついている。すなわち、中小企業は「過少過多」で、効率が悪く、生産性が低い、低賃金でなんとかやりくりしているということが、必ずしもあてはまらない。そうした現場で目の当たりにした事実を積み重ねて研究を進め、「ベンチャービジネス」に行きついたのである。東京大学で学んだ内容と現場の実態に大きな乖離があったことには少なからず衝撃もあったのではないかと想像するが、実態をベースに理論を構想していき、新しい概念を打ち立てている。ベンチャービジネスは、いわば和製英語で、後づけで概念を定義していったものであるが、従来型の二重構造論的な中小企業観とは対照的な、「知識集約的なイノベーターとしての中小企業」をベンチャービジネスと名付けている。ベストセラーとなった『ベンチャー・ビジネス』(日本経済新聞社・1971年・清成忠男、中村秀一郎、平尾光司の共著)が発刊されてからすでに半世紀以上が経過している。日本ベンチャー学会主催「清成忠男先生お別れの会」(2024年9月4日/学士会館)の追悼セッションにおいて、近年、ベンチャービジネスという言葉があまり使われなくなり、「スタートアップ」という言葉が主流になっていることを踏まえて、「日本ベンチャー学会もいずれは、日本スタートアップ学会になってしまうかもしれない」とやや嘆き節的な意見もあった。もし、清成忠男がその場にいたならば、「そんなものは、時代と実態に合わせて、どんどん変えていけばいいんだよ」とおっしゃったに違いない。そうした柔軟性が、清成忠男の新しい構想を生み出した原動力なのではないかと思う。
地域経済研究
第二の「地域経済研究」であるが、清成忠男は「地域主義のルーツをさぐると、昭和48年(1973年)にさかのぼる。」(清成忠男『地域主義の時代』東洋経済新報社・1978年)と著書でのべている。同年に著書で東京大学の玉野井芳郎教授が「地域主義」をはじめて提起している。その後、清成忠男とともに地域主義に関する共著も出版している。戦後の高度成長期に、地方から東京などの大都市に急激な人口移動が起こり、都市への過度な人口集中、公害の発生、地方の衰退が1970年頃から社会問題化しはじめていた。ちょうど第1次石油ショックが発生した1973年は、地域主義のルーツとも符合する。石油ショックで、高度成長を前提とした社会構造は転換を余儀なくされる。あらためて地域の重要性が見直されるきっかけとなったのである。ムラおこし、まちおこし、まちづくり、地域活性化、地方創生と呼び名はいろいろあるが、その原型は沖縄の島嶼部でおこなわれた「シマおこし研究交流会議」であるという。清成忠男はこれにかかわり、後に沖縄振興開発審議会の委員や委員長も務めている。シマおこしがまちおこしに広がり、やがて大分の一村一品運動、大分県の湯布院や北海道池田町をはじめとする全国各地での地域づくりにつながっている。清成忠男は、地域経済研究と中小企業研究を同時期に並行して進めている。中小企業研究を進めていると、地域経済との関係に必ずぶつかる。清成忠男は、あるとき、先輩の研究者から、賀川英夫編著『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』(1943)を読んでいるかと聞かれたという。「読んでいません」と答えると、「それで中小企業を研究しているといえるのか、と怒られた」という。特殊産業というのは、現在でいうところの地場産業である。愛媛県の地場産業について、終戦末期に松山商科大学(現・松山大学)の教授であった賀川英夫とその同僚が、愛媛県の地場産業である伊予絣、四国中央市の製紙産業、砥部焼などについての事例研究をまとめた著書である。地場産業を特殊産業と呼んでいたのは、重厚長大型の主要産業に対しての対照語である。まさしく地域における中小企業の事例研究なのである。地域経済を発展、活性化させることは、すなわち、中小企業の活性化に他ならないのである。賀川英夫は経済地理の研究者で、「新東亜経済地理」などの著書を発刊しているが、『日本特殊産業の展相―伊予経済の研究―』が遺稿となっている。というのも、そのあと、戦時中に台湾に船で渡航しているところを米軍に撃沈され、死亡しているからである。ちなみに、清成忠男の父親が、中央官僚の職をもし辞さなかった場合は、同じ船に乗って死亡していたはずであったとも清成忠男は述べている。その貴重な本は、「君は愛媛県出身だから」という理由で私にいただいた。少しは勉強しなさいという意味だと思い、その著書を起点に、ウッデバラシンポジウム(ロンドン、スウェーデン)で発表させていただいた。ともあれ、清成忠男の地域研究は精力的に続けられ、2008年に発足した地域活性学会の初代会長にも就任している。
大学改革・高等教育振興
大学改革に関する功績は、法政大学総長・理事長としての功績と、さらに高等教育全体への貢献の二つに大別される。清成忠男は、1996年から2005年までの9年間(3期)、法政大学第16代総長として在任した。法政大学の総長は、学校法人法政大学理事長、法政大学学長、付属校を含む学園の長、の三位一体の激務である。教職員の選挙により選出される。本人は、研究が疎かになるので、やりたくもなかったが、余人をもって代えがたいと担ぎ出されて2度目の選挙で当選した(一度目は、在職中に亡くなった阿利莫二総長の残任期間の総長を選ぶ選挙に立候補して落選)。そういうわけで、「総長なんて懲役3年の刑にあったようなもの。入口には看守(秘書)がいて常に行動を監視されて自由がなく、独房(総長室)にはトイレもある。囚人と違うところは服役態度が良ければ刑期(任期)が延びるところだ」と公言していた。しかし、清成忠男が総長に就任する前の法政大学は、大学としては長期にわたる停滞状態が続いていた。
①市ケ谷キャンパスが手狭なために開設した多摩キャンパスへの学部移転問題による深刻な学内対立、入試採点スト騒動などが発生していた。
②18歳人口急増期にあって、新学部設置の設置認可申請を文部省(現在の文部科学省)に3回出して、学内対立を理由に3回取り下げ、大学院の新研究科設置も1回取り下げをした。
③多摩キャンパス開設資金の捻出のため、川崎・武蔵小杉の川崎グラウンドの売却を巡る汚職・不正事件が発生し、マスコミに大きく報道され、受験者数が減少し、その後始末に後任の総長が追われていた。
④学生運動の巣窟として、活動家学生がキャンパスを占拠していた。
これらの様々な大変な状況下で総長に立候補するのは、火中の栗を拾いに行くことに他ならない。清成忠男を総長に担ぎ出すプロデューサーな役割を果たした経営学部教授で総長代行も務めた鬼塚豊吉は、のちに「何をやってもうまくいかない、とシニカルな雰囲気が漂っていたわが法政大学を、よくぞ立て直してくれた(趣旨)」と回顧している。
法政大学における清成改革の骨格は、
①教学改革を主軸とした改革により、6学部から15学部体制への礎を築き、時代のニーズをとらえた学問分野を展開した。
②学生の総定員(収容定員)は変えずに、学部を増やし、専任教員を600名から700名に100名増員して、マスプロ教育から少人数教育へと舵を切った。
③専任職員は600名から400名へ200名に減員し、アウトソーシングを推進した。
④ボアソナード・タワー、外濠校舎をはじめとするキャンパス整備の推進
などがあげられる。
結果として、個性的で多彩な人材が入学する人気大学へと再興したのである。法政大学改革にまつわるエピソードについては、拙著「法政大学改革物語~清成忠男総長時代の改革」(同友館・2014年)にくわしいので、参照いただきたい。
「法政大学中興の祖」としての清成忠男
法政大学150年の歴史を振り返ると、大きな大学経営の危機は3度あり、その危機を救ったのが当時の総長(総理)であった。すなわち、
一、法政大学草創期に、ボアソナード博士が民法典論争に敗れフランスに帰国、フランス法の学校である法政大学も不人気になり、疲弊していた法政大学を、学監・校長・総理として、無報酬で、再興に尽力した梅謙次郎
二、戦災で校舎の大部分が焼失した法政大学を復興し、高度成長期で大学進学者が急増する時代にあって、多くの入学者を受け入れ、社会の中堅を担う人材を輩出た大内兵衛
三、多摩移転による深刻な学内対立、学生運動の余波で、18歳人口急増期にもかかわらず、6学部のまま地盤沈下していた法政大学を、教学改革を主軸とした大学改革により、15学部体制の礎を築き、時代のニーズをとらえた学問分野の展開で、個性的な多彩な人材が入学する人気大学へと再興した清成忠男
3人の総長(総理)は、法政大学の危機に現れて、新しいビジョンを示し、自ら改革を実行して、法政大学の発展に大きな貢献をしてきたのであった。そういう意味においては、清成忠男は、法政大学にとって「中興の祖」「三恩人の一人」と言っても過言ではない。
高等教育振興への貢献
清成忠男は、法政大学のみならず、高等教育振興にも貢献があった。ひとつには、大学基準協会の会長として、大学認証評価制度の基盤整備に尽力したことが挙げられる。従来、日本では、大学や学部の設置は文部省(現文部科学省)の厳格な設置認可審査が行われていた。それが2000年前後の規制緩和により、大学の質保証は、事前審査から事後チェックへと舵が切られていったのである。事後に大学としての質が担保されているかについては定期的に認証評価の受審を義務付けられている。これらの今日では当たり前になっている認証評価の制度設計にあたり、ドイツやアメリカの事例も参考にしながら進めていったのである。二つ目には、大学への指定寄附制度の推進が挙げられる。私立大学連盟の副会長として、企業等からの寄附を大学が受ける場合に非課税とする「指定寄附制度」導入推進に尽力した。現在では、日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)を通じての指定寄附により、全額損金不算入(非課税)となっている。三つ目には、社会人が働きながら大学院に通う「社会人むけ夜間大学院」の先鞭をつけたことが挙げられる。1992年4月に、法政大学は、大学院社会科学研究科経営学専攻で社会人を受け入れるコースを新設しているが、これは、社会人が働きながら、平日夜間と土曜日のみの通学で修士の学位が取得できる、日本で初めての本格的な「社会人むけ夜間大学院」となった。清成忠男は、経営学部教授として設置に携わり、特に日本初となる「企業家養成コース」は当時、大きな注目を集めたのであった。これには伏線があり、清成忠男が経営学部主任を務めていた1980年前後に、同僚の教授有志と、将来の18歳人口減少を見据えて、経営学部独自で議論し、できるところから改革を進めていこうというプロジェクトを立ち上げたことがきっかけとなっている。18歳人口は減少しても、知識基盤社会においては、高度職業人養成の需要が高まり、大学院を中心に逆に需要が増える分野もあるのではないか、という議論がなされた。10年計画で、5年以内に研究所を設立し、産官学連携を進め、10年後にビジネススクールを設立する、というのがその構想であった。構想は、1986年に法政大学産業情報センター(現・法政大学イノベーション・マネジメント研究センター)が設立され、1992年4月に社会人むけ夜間大学院が開設され実現したのであった。夜間大学院の仕組みは、各大学が取り入れはじめ、その後のスタンダードとなった。さらに、法政大学総長退任後の2014年から2年間、事業構想大学院大学の学長に就任し、これまでにない、新しいタイプのビジネススクールの創立期を支えたのであった。事業構想大学院大学は、宣伝会議をはじめとする10数社の企業グループを経営する東英弥が2012年に文部科学大臣の認可を得て東京・青山に設立した社会人向けの大学院である。連続起業家である東英弥は、「事業構想により、社会の一翼を担う構想人材を輩出する」という理念をかかげ、私財を投じて大学院を設立し、理事長に就任している。清成忠男は、文部科学省への設置認可段階からこれまでの経験を踏まえてアドバイスを行った。2012年の開学から授業科目を担当し、さらに2014年から2年間、二代目の学長を務めたのであった。清成忠男は生前「この大学院は、東理事長の企業家としての思いでつくられた大学院であり、野田一夫先生(初代学長)と私が関わっている以上、成功させないわけにはいかない」と常々語っていた。時には理事長の東英弥と意見がぶつかることもあったが、「大学の将来のために嫌われ役もあえてやる」と、熱意をもって取り組んでいたのが印象的である。現在では事業構想大学院大学も、社会構想大学院大学とあわせて、社会人ビジネススクールの一翼を占める大学院へと成長している。
定説にとらわれない柔軟な発想
清成忠男は、「定説」「常識」とされている事象をそのまま受け入れるのではなく、現場からえられた情報から事象を分析し、新たな「学説」を構想して提唱し続けた。時には異端児扱いされたこともあったであろうが、結果として、時間の経過とともに自らの学説が「定説化」していっている。80才代後半になっても、常に最新の事象や情報入手を心がけていた。パソコン操作は決して得意ではなかったが、奥様の協力も得ながら、ドイツをはじめとするヨーロッパ、アメリカのベンチャービジネスの動向、高等教育の動きを常にチェックしていた。 また、通常ではありえないような「犬猿の仲」といわれるような人物同士をとりもつコーディネート能力にもたけていた。どんな人とも付き合い、話を聞くが、一方で愛想やお世辞は言わない、といった姿勢を貫いた。これらの一見、関連がないようにみえる分野を、自らの専門分野とし、それぞれを有機的に結合する柔軟な発想や姿勢が、研究者としての構想力として結実したのであろう。(文中敬称略)
白石史郎 清成ゼミ23期生・1995年法政大学経営学部卒。2003年法政大学大学院社会科学研究科経営学専攻企業家養成コース修了。2018年法政大学大学院政策創造研究科博士課程満期退学。事業構想大学院大学事務局長(地域校統括)
清成 忠男(きよなり ただお)
1933.2.19-2024.7.23(享年91歳)
略歴 1933年東京都生まれ。法政大学総長・理事長、事業構想大学院大学第二代学長を務めた。中小企業論、地域経済論の大家で、「ベンチャービジネス」の和製英語生みの親の1人。
1956年東京大学卒業後、国民金融公庫(現・日本政策金融公庫)勤務を経て、1996年より9年間、法政大学総長・理事長を務める。大学改革を推進し、6学部から15学部へ再編する足掛かりをつくった。在任中に市ケ谷キャンパスに27階建ての都心型キャンパス「ボアソナード・タワー」を竣工(2000年)、受験者がはじめて9万人台を突破(2003年)し、「改革の法政」のイメージを浸透させ、長期にわたって停滞していた法政大学の「中興の祖」ともいえる実績を残した。日本私立大学連盟副会長、大学基準協会会長を務め、高等教育全体の振興のための政策提言を積極的に行い、大学への寄付の非課税措置(私学事業団を通じた指定寄附制度)導入にも尽力した。1999年の小渕内閣での中小企業基本法の抜本改正では、中小企業政策審議会基本政策部会会長として携わり、中小企業弱論にもとづく保護政策から、意欲あるベンチャー企業やスタートアップ支援への政策転換をはかった。日本ベンチャー学会を立ち上げ、初代会長を務めた。地域経済分野では沖縄振興開発審議会会長、沖縄協会会長を務め、沖縄はじめ全国各地の地域活性化政策に携わるとともに、地域活性学会初代会長を務めた。法政大学総長・理事長退任後は、2014年から2年間、社会人向けビジネススクールである事業構想大学院大学学長を務め、新事業創出、地域活性人材の輩出に尽力した。2010年、瑞宝大綬章受章。専門は中小企業論、ベンチャービジネス論、地域経済論、比較経済論。『日本中小企業政策史』『現代日本の大学革新』『地域創生への挑戦』『ベンチャー・ビジネス』など著書多数。
略年表
1933年2月19日 東京都生まれ。
1956年3月 東京大学経済学部経済学科卒業
1956年4月 国民金融公庫(現・日本政策金融公庫)入職。新宿支店、調査課長
(1973年3月まで)
1968年4月 法政大学経済学部兼任講師(1969年3月まで)
1972年4月 法政大学経営学部助教授
1973年4月 法政大学経営学部教授
1986年4月 法政大学経営学部長(1988年3月まで)
1990年4月 法政大学産業情報センター(現・法政大学イノベーション・マネジメント研究センター)所長(1995年3月まで)
1992年4月 法政大学大学院社会科学研究科経営学専攻企業家養成コース兼担
(日本初の社会人向け・夜間大学院「企業家養成コース」)
1996年6月 法政大学総長・理事長(2005年3月まで、3期9年間)
2005年4月 法政大学学事顧問(2014年3月まで)
2014年4月 事業構想大学院大学・第二代学長(2016年3月まで)
2024年7月23日 逝去(享年91歳)従三位
主な公職歴
中小企業政策審議会 基本政策部会会長
沖縄振興開発審議会会長
中央酒類審議会会長
大学基準協会会長
日本私立大学連盟副会長
日本ベンチャー学会会長(初代)
日本キャリアデザイン学会会長(初代)
地域活性学会会長(初代)
三鷹ネットワーク大学推進機構理事長
叙勲等
フランス教育功労章コマンドール勲章(2006年)
瑞宝大綬章(2010年)
従三位(2024年)
主要著書
中小企業・ベンチャー関係
『現代日本の小零細企業』(文雅堂銀行研究社・1967年)
『倒産』(金融財政事情研究会・1967年)
『日本中小企業の構造変動』(新評論・1970年)
『ベンチャー・ビジネス』(日本経済新聞社・1971年・共著)
『中小企業・円切り上げ経営政策』(ダイヤモンド社・1971年・共著)
『現代中小企業の新展開』(日本経済新聞社・1972年)
『ベンチャーキャピタル』(新時代社・1972年)
『中小企業の知識集約化戦略』(日本事務能率協会・1973年・共著)
『知識集約産業』(日本経済新聞社・1974年)
『日本流通産業の革新』(新評論・1974年)
『現代経済問題の基礎知識』(有斐閣・1974年・共編著)
『変動期の中小企業経営』(日本労働協会・1975年)
『現代中小企業論』(日本経済新聞社・1976年)
『現代日本経済史』(筑摩書房・1976年・共著)
『企業提携』(日本経済新聞社・1977年・共著)
『中小企業論』(有斐閣新書・1978年・共著)
『経済学のフロンティア』(東洋経済新報社・1978年・共編著)
『中小企業読本』(東洋経済新報社・1980年)
『企業家革命の時代』(東洋経済新報社・1982年)
『現代中小企業史』(日本経済新聞社・1982年・共著)
『都市型中小企業の新展開』(日本経済新聞社・1982年・共著)
『経済活力の源泉』(東洋経済新報社・1984年)
『中小企業』(日本経済新聞社・1985年)
『ハイテク時代の中小企業』(ぎょうせい・1985年・共編著)
『アジアの挑戦』(東洋経済新報社・1991年・共編著)
『改正大店法時代の流通』(日本経済新聞社・1991年・共編著)
『現代の系列』(日本経済評論社・1992年・共編著)
『中小企業ルネッサンス』(有斐閣・1993年)
『スモールサイジングの時代』(日本経済評論社・1993年)
『ベンチャー・中小企業優位の時代』(東洋経済新報社・1996年)
『中小企業論』(有斐閣・1996年・共著)
『日本型産業集積の未来像』(日本経済新聞社・1997年・共編著)
『企業家とは何か』(シュンペーターの訳書・1998年・東洋経済新報社)
『中小・ベンチャー企業研究30年 時代を映す』(日経事業出版センター・2004年)
『日本中小企業政策史』(有斐閣・2009年)
『事業構想力の研究』(事業構想大学院大学出版部・2013年)
地域経済関係
『地城の変革と中小企業』(日本経済評論社・1975年)
『地域と中小企業金融』(日本経済評論社・1977年)
『地滅主義の時代』(東洋経済新報社・1978年)
『地域主義』(学陽書房・1978年・共編著)
『地域への視角』(日本経済評論社・1979年・共編著)
『地域の文化を考える』(日本経済評論社・1980年・共著)
『地域社会と地場産業』(日本経済評論社・1980年・共編著)
『地域自立への挑戦』(東洋経済新報社・1981年)
『80年代の地域振興』(日本評論社・1981年)
『わが町わが産業』(清文社・1981年・共編著)
『地域主義の構想』(学陽書房・1981年・共編著)
『地域小売商業の新展開』(日本経済新聞社・1983年)
『地域産業政策』(東京大学出版会・1986年)
『地方の時代の経済学』(日本放送出版協会・1986年)
『地域づくりと企業家精神』(ぎょうせい・1986年・共編著)
『地域再生のビジョン』(東洋経済新報社・1987年)
『グローバル時代の地域づくリ』(ぎょうせ い・1989年)
『地域における大学の役割』(日本経済評論社・2000年・共編著)
『地域創生への挑戦』(2010年・有斐閣)
高等教育関係
『21世紀の私立大学像 』(法政大学出版局・1999年)
『21世紀私立大学の挑戦』(法政大学出版局・2001年)
『大淘汰時代の大学自立・活性化戦略』(東洋経済新報社・2003年)
『現代日本の大学革新』(法政大学出版局・2009年)
回顧録
『学びの軌跡』(有斐閣アカデミア・2011年)
追悼行事
日本ベンチャー学会主催「清成忠男先生お別れの会」2024年9月4日(学士会館)
地域活性学会主催「清成忠男先生を語る会」2024年12月5日(私学会館)
法政大学主催「法政大学元総長清成忠男先生お別れの会」2024年12月5日(法政大学薩埵ホール)