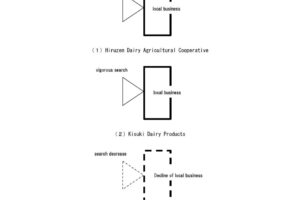秋谷公博(高知県立大学)
高知県立大学の秋谷公博と申します(写真①)。2024年に地域活性学会に入会いたしました。長い間、タイやラオス等のスラムや野宿者らが主体となって行っているまちづくりについて当事者であるスラム住民の方々らと衣食住を共にしながら調査研究を行ってまいりました。近年では、ポップカルチャーを活用したまちづくりや、チーム基盤型学習と課題解決型学習を活用したまちづくり分野等における教育に関する研究等も行っております。長年「まちづくり」関連の研究を行ってまいりましたが、その分野に興味を持つようになったのは、①大学を1年間休学して、バックパッカーとしてユーラシア大陸を1周した経験と、②復学後タイの都市問題をテーマとしたサマーワークショップへの参加が経緯となっております。
ユーラシア大陸1周の旅
ユーラシア大陸1周の旅では、故郷の埼玉県から山口県の下関まで鈍行列車を乗り継ぎ、フェリーで韓国の釜山に渡った後に、仁川から中国の青島に渡り、そこからアジア大陸を横断しました。その後、ヨーロッパ大陸を北上してエストニアからロシアに入り、シベリア鉄道でモスクワから中国の北京へ、その後天津からフェリーで韓国の仁川、釜山を経て下関に戻るという旅程をタイ→バングラデシュ→インドの区間を除いて、徒歩、バス、鉄道、フェリーを利用して約7か月間旅をしました。旅行中には、様々な国の文化や史跡等に触れるだけでなくコソボ紛争による傷跡をはじめ、開発途上国では小さな子ども達が働かされているという現状や、アジアのスラム等の貧困層の居住地区では、粗末な住宅が過密化し、劣悪な環境下で生活を余儀なくされている人々がいるという現状も目の当たりにしました。その一方で、過酷な生活を送っている人々が日々を精一杯生きている姿を見て感銘を受けました。
タイの都市問題に関する調査研究
大学復学後に母校が実施したサマーワークショップに参加し、2週間タイの都市問題に関する調査研究を行いました。そこでは、スラム住民が抱えている問題が山積していること、それらを改善するために住民が主体的にまちづくりに取り組んでいる姿を目の当たりにし、そこで生活している人々の目線で地域課題を捉えることの大切さを痛感しました。これらの経験から、私が研究や教育で心がけているのは「地域の人々の目線」で問題を捉えるということです。修士論文や博士論文のための現地調査や、大学教員になってからも現地調査に行くたびにスラム住民の住宅にホームスティをしながら調査研究を実施しました。ホームスティをしていた際には、時には生活習慣や文化の違いや言葉の問題などで戸惑うこともありましたが、タイの方の大らかさと温かさを知る機会となり、その後の人生においても大きな財産となっております。

タイのホストファミリー
現在では、アジアのまちづくりの経験をもとに、日本のまちづくりに関する研究等に取り組んでおります。これらの研究でも「地域の人々の目線」で物事を捉えるように心がけております。この心構えは、現職の高知県立大学の担当科目の教育においても意識しております。現職の高知県立大学は地域志向の大学「県民大学」として、「大学が地域を変える、地域が大学を変える」との地域志向の理念である「域学共生」を標榜し、共通教養教育科目で「域学共生科目」を設け、その科目代表等を務めております。これらの実習や本学が実施している学生主体の活動である「立志社中」等を通して、地域の皆様が笑顔で元気に日々生活できるような地域づくりを目指して、地域の方々と共に取り組んでおります。
「域学共生科目」で全学部1回生の必修科目の一つである「地域学実習Ⅰ」では、「地域の課題を肌で感じる」をテーマとして、学生が座学や事前学習、現地実習、その後の事後学習をもとに地域の人々との交流や調査研究を通して地域についての理解を深めることを目的として実習を行っております。

地域学実習Ⅰの様子
その他に、3回生以上を対象とした「域学共生実習」では、学生がフィールドワークを通して地域課題等を明らかにし、その改善に向けて地域の皆様と取り組んでおります。2024年には、学生が高知県高知市春野にある集落センター仁ノ万葉の里や地域の特産品等の知名度向上を目的として日曜市への出店を地域の方々に呼びかけ、2024年12月8日に仁ノ万葉の里等で収穫した野菜の販売や、学生が作成した紹介チラシの配布、名産品の「トラまき」の紹介などを始めとしたPR活動等を住民の皆様らと協働で行いました。その様子は2024年12月8日のNHK NEWSで「高知 大学生と住民が協力 日曜市に初の出店」として取り上げられております。

日曜市出店の様子
今後も、大学教育や調査研究を通して学生が地域から学び成長することができる機会や、地域の皆様が学生と関わりを持つ機会を創出することで、地域の皆様が元気になれるように、「地域の人々の目線」を大切にした学生、地域の皆様双方にとって良い機会づくりに取り組んでまいりたいと存じます。