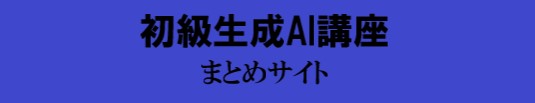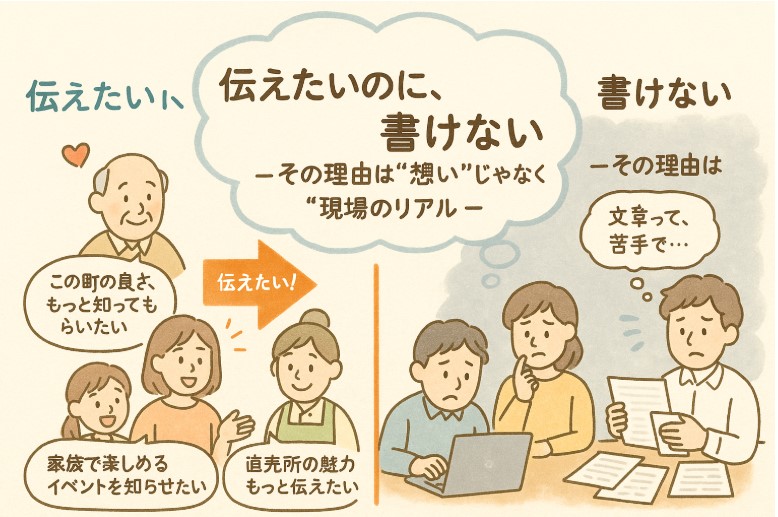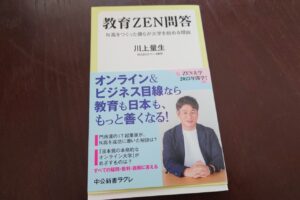第3章:実践的なAI活用(テキスト・画像・データ分析)
- 文章生成AIの活用
- 画像生成AIの活用
- AIによる市場調査とデータ分析
はじめに ― 書けないのは、思いがないからじゃない
「この町のこと、もっとたくさんの人に知ってほしい」
「いい催しを、もっと来てほしい人に伝えたい」
そんなふうに願っている人は、地域にはたくさんいます。
でも現場でよく聞くのは、こんな声です。
- 「時間がなくて手が回らない」
- 「文章って、苦手で…」
- 「正しい情報が多すぎて、どう書けばいいか迷う」
思いはあるのに、ことばにするのがむずかしい──そんなとき、**文章生成AIは“クラッチ”**みたいなものです。
つまり、頭の中のイメージと、地に足ついた文章との間をつなぐ「中間装置」。
この章では、その“つなぎ方”を、なるべく具体的にお話ししていきます。
1. 地域発信に、AIがなじむ理由
たとえば、こんな場面を想像してみてください。
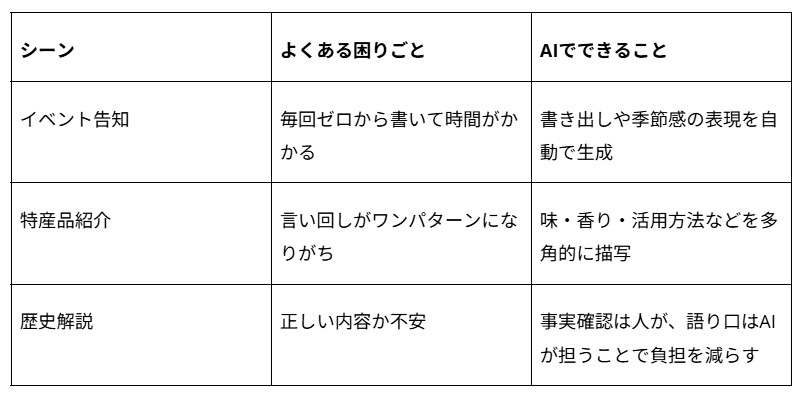
AIは「ゼロから何かを生み出す」ことも得意ですが、
本当に大事なのは、**「最後に自分たちの声に戻す」**という作業です。
つまり、“AI任せきり”ではなく、“一緒に書く”というスタンス。
そのための具体的な方法を、次のセクションでご紹介します。
2. ChatGPTを使った3つの現場シナリオ
2‑1 イベント告知文 ― 「ぬけもれ」と「らしさ」をどう両立するか
❌ よくある声
「AIに“桜まつりの告知を書いて”って言ったら、花火があるって書かれちゃって…うちはやらないのに!」
よくあるんです。情報が少ないと、AIが想像で補ってしまう。
それを防ぐには、必要な材料をちゃんと渡すことが大切です。
✅ 具体的な伝え方(プロンプト)
【目的】4月10日開催の「桜まつり」の告知文
【形式】見出し+本文200〜250字
【必須情報】
・○○公園(駅から徒歩8分)
・模擬店15店/地元中学生のブラスバンド演奏/夜桜ライトアップ
・主催:○○町観光協会
【トーン】家族連れ・観光客向け/やさしく敬語で
【禁止】花火やキッチンカーなどは記載NG
【追加】文末に問い合わせ先(TEL&Web)
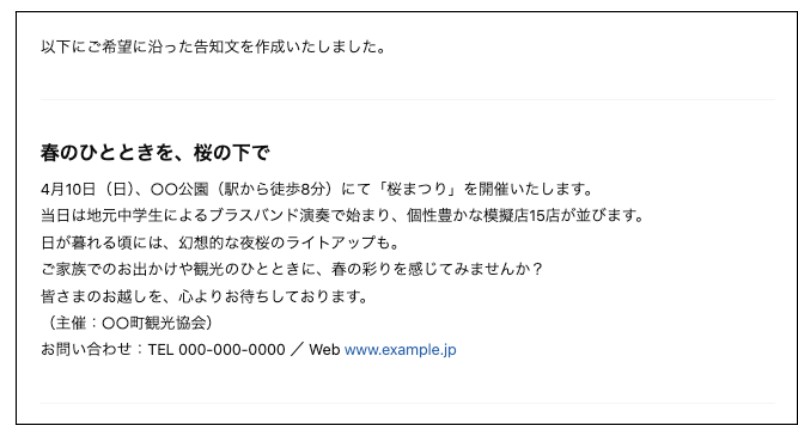
こうやって材料をそろえておくと、安心してAIに任せられるんです。
「AIを信じる」のではなく、「AIに伝わるように話す」のがコツですね。
2‑2 特産品紹介 ― 「甘い」だけじゃ伝わらない
たとえば「いちごがおいしい」だけじゃ、正直どこの町も言ってることになってしまいます。
でも、何がどうおいしいのか、どう楽しめるのかが伝わると、ぐっとイメージが湧いてきます。
🎯 こんなプロンプトはいかが?
【目的】観光ブログ(SEOキーワード:○○町 いちご狩り)
【長さ】800〜1,000字
【伝えたい魅力】
① やわらかな果肉 ② 糖度13度以上 ③ 気軽に摘み取り体験できる
【出典】町の公式サイト/JAのパンフレット
【誘導】予約リンクあり(押しつけ感なし)
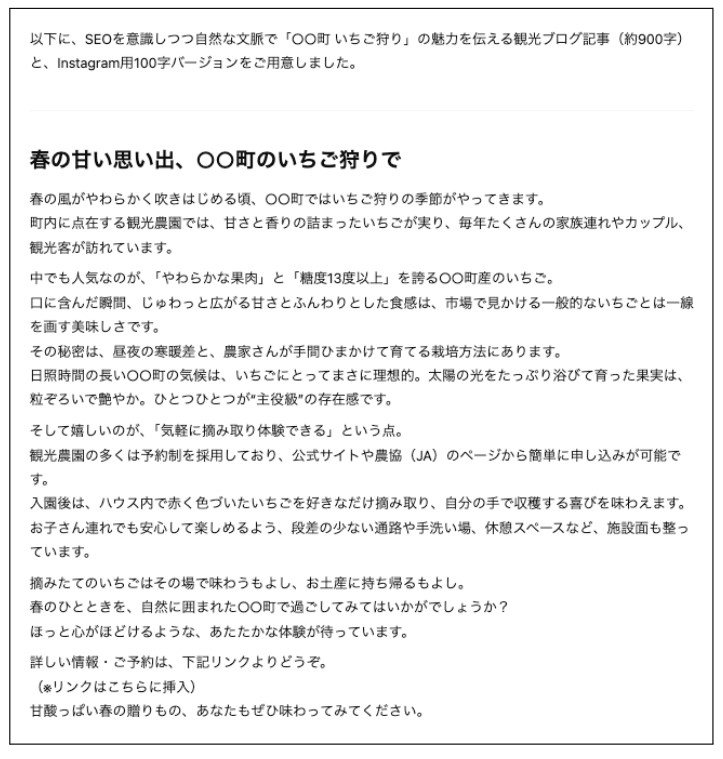
AIに「本文」と「チェックリスト」の両方を出してもらえば、人が手直ししやすい原稿になります。
3. AIと人の分担事例
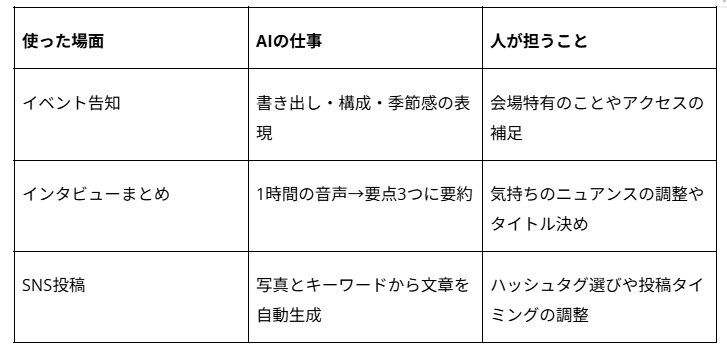
4. AIに指示する前に立ち止まってみるチェックリスト
- 誰に伝えたい?(どこに住む、どんな人?)
- 何を感じてほしい?(行動?共感?学び?)
- 事実として外せないのは?(数字・名前・出典)
- AIにまかせる範囲を決めた?(構成・文章・要約)
AIが出力したあとは
- 最後に“地域の色”を戻した?(方言・写真・語り口)
おわりに ― AIは、あなたの声を大きくする相棒
AIは、「あなたの声を奪うもの」ではありません。
むしろ、声を整理して、遠くまで届くようにしてくれる道具です。
ただ、最後にもう一度、自分の目で読み、自分の手で手触りを戻す。
そのひと手間が、読み手との信頼をつくります。
「書けない」「時間がない」と感じたときこそ、
伝えるっておもしろいを取り戻すチャンスかもしれません。
よかったら、この章に出てきたプロンプトを試してみてください。
あなたの言葉が、きっと誰かに届きます。