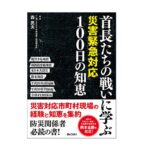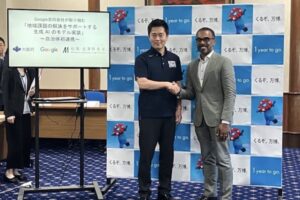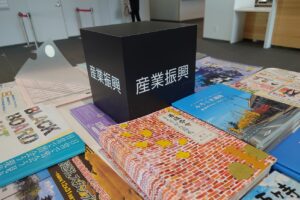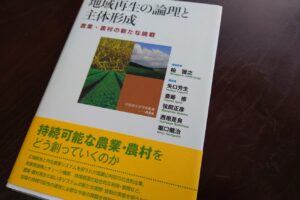坂本祐子
みなさま、こんにちは。地域活性学会正会員の坂本祐子と申します。私は群馬パース大学、県民健康科学大学、群馬大学などで非常勤講師を務め、主に社会学の講義を担当しています。また社会活動として、一般財団法人ぐんま未来基金(以下ぐんま未来基金)の理事を務めていますので、今回はぐんま未来基金の活動をご報告したいと思います。
コミュニティ財団って何ですか?
ところで、みなさまは「コミュニティ財団」という言葉を聞いたことがありますか。1年程前、ぐんま未来基金に協力してもらえないか、とお声がけいただいた時には私は「コミュニティ財団って何ですか?」という状態からのスタートでした。一般社団法人全国コミュニティ財団協会によれば、コミュニティ財団は「地理的な『コミュニティ=地域』を特定して、複雑かつ重層的に絡み合う地域の諸課題を包括的な視座に立って事業対象とし」、 「予防的な対応を含む有効な事業に対して、資金をはじめとする資源を仲介・提供し、ひいてはその地域内の多様な背景を持つ住民の暮らしの質を高めるために貢献する組織」と定義されています1)。つまり、コミュニティ財団は、地域の様々な人が寄付をして設立する市民による地域のための財団であり、自分たちの手でまちを良くするための仕組みです。市民のみなさんからのご寄付を地域で活動する団体に助成して支えていくことが主な仕事です。小関(2024)によると、2023年12月時点で、コミュニティ財団は全国に48あるそうです2)。私が住む群馬県では初となるコミュニティ財団「ぐんま未来基金」は、設立準備会を経て群馬県内外の337名の設立賛同人のもとに2024年3月に一般財団法人として設立されました。設立にあたっては、(一社)全国コミュニティ財団協会を通じて、休眠預金を活用させていただき、多大なるご支援をいただきました。

一般財団法人ぐんま未来基金を設立
ぐんま未来基金の伴走支援
ぐんま未来基金では、「設立記念助成プログラムA」として団体の寄付集めの力をつけるマッチングギフト型の助成を、「設立記念助成プログラムB」として地域の力になりたいと活動する若者・学生団体向けのプログラムを準備しました。この助成プログラムを考えるのは主にプログラムオフィサー(PO)の仕事です。POは、地域で活動している団体の声を聞き、いま地域の人々は何に困っていて地域には何が不足しているのか、どのようなプログラムを準備したらよいのかを考えます。単に資金を助成すれば良いというものではなく、非資金的支援として団体への伴走支援も行っていきます。今回の「プログラムA」には、共働きの子どものいない夫婦(DINKs)の多様な価値観や生き方が尊重される社会の実現を目指して活動する「フタリテ」という団体と、海外ルーツの家庭にスポットライトを当て、子どもやその保護者が安心して暮らすことができる地域を目指す「NPO法人ともに暮らす」という2団体が採択されました。「プログラムB」にもチャレンジしたい学生団体から多くの応募があり、6団体を採択しています。これらの採択された団体同士の横のつながりもでき、一緒にイベントを行ったりしてお互いに刺激になっているのもとても嬉しいことでした。新聞等のメディアにも各団体の活動が取り上げられ、今年の2月には採択された計8団体の活動報告会も行いました。自分たちの活動によって地域にどのような変化があったのか等を発表するとともに、寄付者の皆様への感謝の意を表しました。助成団体からも「ぐんま未来基金のおかげで活動の幅が広がった」、「ぐんま未来基金があって良かった」という声をいただき、寄付者の方からも「自分たちのお金の使われ方が良く分かって嬉しい。これからも寄付を続けたい」といった声を聞くことができました。私達も改めて自分たちの活動の意味を考える契機となりました。

活動報告会
助成団体への授与式にて実施したワークショップ
まだ顕在化していない課題に気づいて行動している人を支える
現在、ぐんま未来基金では、新たに「地域別支援プログラム」として各地域の課題解決に挑む団体を公募しています。言うまでもなく地域の課題は様々です。その課題は既に知られているような課題とまだ多くの方には知られていない課題があります。まだ顕在化していない課題に気づいて行動している人を支えるコミュニティ財団として、私達も認知度を高められるように活動していきたいと思っています。みなさまがお住いの地域にもきっとコミュニティ財団があると思いますので、関心をお寄せいただけると幸いです。
坂本祐子(地域活性学会正会員)