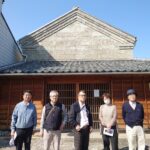明治26年の大火を契機に多くの蔵が建てられた
川越市は、埼玉県に位置する重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)として知られています。この地区は、歴史的な町並みや文化財を保存するための取り組みが行われており、特に「蔵造り」と呼ばれる伝統的な建築様式が特徴です。川越市の重伝建地区は、1999年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。この地区は、江戸時代から続く商業都市としての歴史を持ち、特に蔵造りの町並みが保存されています。蔵造りは、火災に強い土蔵を利用した建築様式で、明治26年(1893年)の大火を契機に多くの蔵が建てられました。 川越市の町並みを特徴づける建物で、黒漆喰塗の外壁が目を引きます。多くの伝統的な店舗が並び、年間約700万人が訪れます。川越市の町割は、寛永年間(1624~1643年)に整備され、現在もその形態が保たれています。川越市では、住民主体のまちづくりが進められており、町並み委員会が中心となって「町づくり規範」を策定しています。この規範は、町並みの保存や新たな建築に関する基準を定めており、地域の景観を守るための重要な指針となっています。
喜多院にお参りしてからまち歩きをスタート
喜多院(きたいん)は、埼玉県川越市に位置する天台宗の仏教寺院で、830年に創建されました。元々は無量寿寺という名前で、江戸時代には徳川家との深い関係を持つ重要な寺院として知られています。特に、江戸城から移築された建物が残っており、これらは現在、江戸城の唯一の遺構とされています。喜多院は、特に540体の石像「五百羅漢」で有名です。これらの像はそれぞれ異なる表情を持ち、訪れる人々にユーモアを提供します。また、春には桜が美しく咲き誇り、訪問者を魅了します。西武線本川越駅から徒歩約15分、東上線川越駅から徒歩約20分です。


鯉のぼりがきれいな大正浪漫夢通りでお茶する



年間700万人の観光客を受け入れる蔵造りの町並みを歩く






お昼に時の鐘を聞く
時の鐘は、埼玉県川越市の中心部に位置する象徴的な鐘楼であり、江戸時代から続く歴史的な建物です。この鐘楼は、川越の蔵造りの街並みの中で特に目立つ存在で、地元の人々に親しまれています。時の鐘は、1627年から1634年の間に川越藩主の酒井忠勝によって建設されました。以来、何度かの火災に見舞われながらも再建され、現在の構造は1894年に完成した4代目のものです。この再建は、1893年の川越大火の後に行われ、地元の商人たちが資金を集めて行いました。時の鐘は、高さ約16メートルの木造三層構造で、内部には約700kgの鐘が設置されています。鐘は、毎日4回(午前6時、正午、午後3時、午後6時)に自動で鳴ります。この鐘の音は、1996年に環境省によって「残したい日本の音風景100選」に選ばれています。