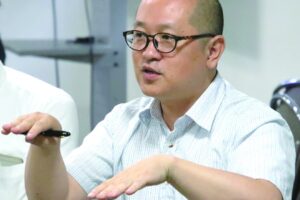このたび、優秀博士論文賞という大変栄誉ある賞を賜り、光栄に存じます。学会関係者の皆様をはじめ、博士学位論文執筆にご協力いただいた皆様に改めまして感謝申し上げます。
公務員生活で培った視点
私は京都府内の地方自治体に勤務する公務員で、現在22年目となります。これまで、駅前の土地区画整理事業、介護保険事業、市民税課税業務、交通政策業務に従事しました。そして、現在は市長秘書として7年目を迎えています。市長秘書という職務柄、市政を俯瞰的に観察する機会が多く、まちづくりの原動力は「人」であることを改めて痛感しています。デジタル化が急速に進む現代社会ではありますが、やはり、「人」同士のリアルな、顔を合わせた対話が重要と感じています。そして、次の四つの「目」を持ち、まちの風(市民の声)を常に意識し、職務にあたることが大切だと感じています。
一つ、「鳥の目」(高いところから俯瞰して見る)。
二つ、「虫の目」(近くで注意深く、細かく見る)。
三つ、「魚の目」(周りを見て、時流を読む)。
四つ、「コウモリの目」(固定観念を外し、相手の立場から逆さに見る)。
なぜ、公務員の私が博士号取得をめざしたのか
今から15年ほど前、私は市役所の先輩から「井の中の蛙になってはいけない」とアドバイスされ、その先輩の誘いで外部の勉強会に参加するようになりました。そこでは、自らの視野の狭さ、知見の無さを痛感しました。そして、学び直しをするために、社会人コースのある大阪市立大学(現大阪公立大学)の修士課程に飛び込みました。ここでは、様々なまちづくりの成功事例をベースに、理論や手法を学び、人脈を広げることができ、自分の世界観が変わる瞬間を体感しました。フィールドワークを中心に修士論文も執筆し、とても充実した2年間でした。ところが、皮肉にも、こうした学びを深めるほど、また人脈を広げるほど、公務員であり続けることへの疑問と、自分は何者かという自問が続きました。公務員である自分は、様々な行政分野に携わり、「組織人」としての経験はそれなりに積んできましたが、他に主張できる「個(自分)」の特技、専門分野はあるのか。そんな自問自答が続いていました。修士課程修了後から数年が経ち、居ても立っても居られず、修士課程でお世話になった大阪公立大学の博士後期課程へ入学することに決めました。それから3年、多くの方のお支えのもと博士学位論文をまとめ、令和7年3月に博士号を授かったところです。博士学位論文は、自分の関心事であった交通政策分野で、修士研究をベースに取り組みました。バスドライバー不足等を背景に全国各地でバス交通の縮退が加速する中で、地域の交通手段をどう確保していくか、まちづくりの現場でも本当に喫緊の課題で、深刻な現状にあると感じていました。その解決に向けて、自動運転システムによる公共交通サービスに着眼し、都市経営論を切り口に社会実装に向けた方途をまとめました。博士学位論文の執筆では、苦悩や達成感などが乱高下し、とにかく知的体力を消耗する作業の連続でした。今、改めて読み返すと未熟な点が多々見受けられますが、本当にこの上ない達成感を得ることができ、貴重な経験となりました。そして、当学会から表彰いただいたことは、本当に今後の大きな励みとなりました。

実務家研究者「JK」として
実務家の強みは、地域課題を日々の業務から捉えていることだと思います。ですが、それを論理的に、学術的に論文にまとめ、広く世の中に問うことが苦手だと言えます。私は、博士号を持った現役公務員という、なかなかレアな存在かもしれませんが、実務と学術の両利きの「実務家研究者」のスタートラインに立つことができました。今後も、公務員生活で培った「目」と「博士号」を持つ実務家研究者として、地域課題の解決に向け取り組むとともに、地域活性学大系の構築に一層貢献できるよう取り組んでまいります。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。