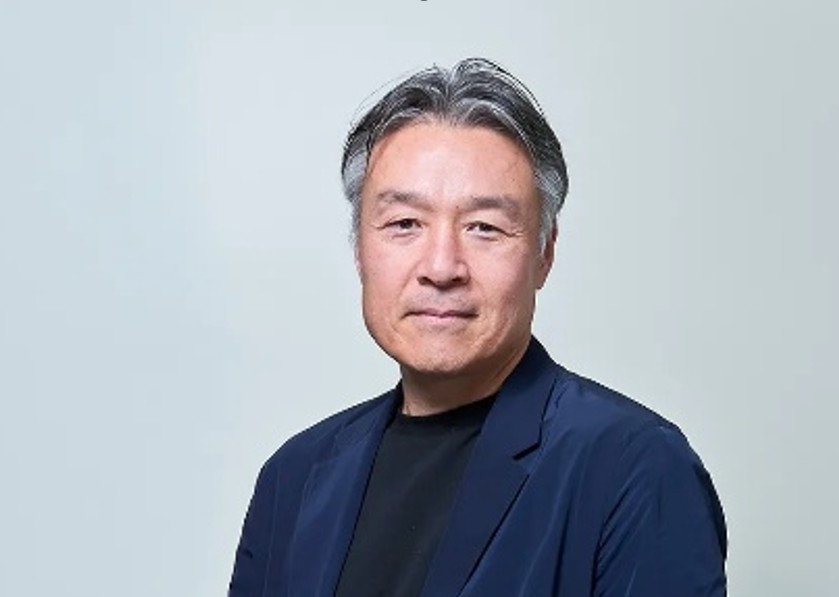國村 太亮
このたび地域活性学会に入会いたしました、國村 太亮(くにむら だいすけ)と申します。51歳での新参者ですので、自らを「学会オールドルーキー」と名乗っています。実務の現場で積み重ねた経験をベースに研究の道に飛び込みました。学会の皆さまと学び合えることを心より楽しみにしております。
実務から研究へ
これまで四半世紀にわたり、フィリップス、アマゾン、セールスフォースといった外資系企業で、マーケティングや事業開発に携わってきました。直近まではセールスフォース・ジャパンにて企業向けのDXコンサルタントを務め、地方企業の支援にも関わりました。現場で痛感したのは、変革の必要性が大きいにもかかわらず、地方ではなかなかDXが進まないという現実でした。学問の世界に関心を持つようになったきっかけは2008年、カナダ・モントリオールのマギル大学MBA留学です。知的好奇心をかき立てる教授陣の指導に触れ、「自分もいつか教育・研究の道に」と心に刻みました。当初は50代後半での転身を描いていましたが、三条市立大学とのご縁により、予定を早めることとなりました。
三条市立大学との出会い
三条市立大学は、新潟・燕三条にある開学5年目の新しい公立大学です。工学部経営工学科のみを有する小さな単科大学ですが、ものづくりの盛んな地域に根ざし、産業界と密接に連携しています。創立間もない頃、知人を介して現学長のアハメド・シャハリアル先生と知り合い、客員教授としてマーケティングの講義を担当しました。その後2年間は、会社員と大学講師の二足のわらじを履く生活でした。学長が口にする「この小さな大学から社会変革のリーダーを育てたい」という言葉に触れるうち、私自身も強く共感し、大学教員としての道に専念することを決意しました。現在は、マーケティング、経営組織論、ロジカルシンキング演習を担当し、研究と教育に取り組んでいます。
研究テーマと問題意識
私の研究関心は大きく三つに整理できます。
- マーケティング:地方企業が市場で持続的な競争優位を築く方法
- 地域企業の活性化:中小企業の成長モデルや地域ブランドの形成
- 企業のDX:人口減少や労働力不足のなかでのデジタル活用と組織変革
特に地方企業のDX推進は、実務経験から得た強い問題意識とつながっています。リクルートワークス研究所の『働き手不足1100万人の衝撃』では、2040年に1100万人の労働力不足が生じると予測されています。その大部分は地方で起こるとされています。まさに地方企業が直面する現実をどう乗り越えるか――その答えを探ることが私の研究の原動力です。
未来志向での研究
ただし、私は課題を悲観的に語るのではなく、未来志向で考えたいと思っています。地方企業には数多くの成功事例や新しい挑戦があります。そうしたポジティブな取り組みを見つけ出し、学術的に整理し、横展開できる形で発信することが、研究者としての使命だと考えています。地域活性学会は、研究者だけでなく自治体や実務家も参加するユニークな場です。多様な視点が交わるこのコミュニティで、皆さまの知見から多くを学びつつ、私自身の経験や研究成果も還元していきたいと考えています。地方企業や地域の奮闘を未来志向で捉え、その成果を広く共有することができれば幸いです。これからどうぞよろしくお願いいたします!
國村 太亮(くにむら だいすけ)三条市立大学 教授|経営修士(MBA)
神奈川県出身。2009年、カナダのマギル大学MBAを取得。帰国後、外資系の自動車ティア2メーカーの市販部門カントリーマネジャーに就任し事業PL管理に携わる。以降、グローバル企業各社で事業開発、デジタルマーケティング、ECビジネスや企業のデジタルトランスフォーメーションに従事。マサチューセッツ州立大学のオンラインMBAのマーケティング講師も務める。三条市立大学では、2023年より客員教授として「マーケティング論」「プロジェクト演習」を担当し、2025年4月より現職

カナダ留学中に所属していたマギル大学MBAラグビークラブの仲間と記念撮影(2009年4月)。観戦のみですが今でもラグビーが大好きです!

ゼミ生との研究活動の様子。地元の日本酒メーカーのSNSマーケティングコンテンツを制作中。

先日の研究大会の懇親会で武蔵野大学の保井教授と学会員の奥山さんと記念写真。これからもよろしくお願いします!

地元紙の三條新聞での寄稿。月に2回のペースで新米教授の奮闘記を燕三条市民の皆さんにレポートしています。