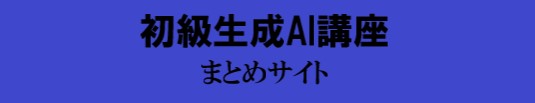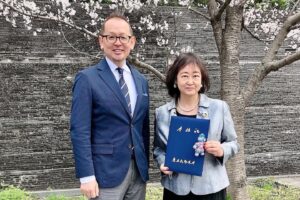この挿絵はGPT4oで作成
第2章:生成AIの基礎スキル
- プロンプトエンジニアリングの基礎
- 地域向けプロンプトの作成
- 地域データの収集と活用
はじめに:地域を語る力と生成AIの可能性
地方創生の現場では、「いかに地域の魅力を外に伝えるか」が常に問われています。人口減少や高齢化が進む中、地域外からの関心や参加をどう呼び込むかは、自治体や関係者にとって大きな課題です。そんな中、ChatGPTのような生成AIは、誰もが手軽に情報を発信できるツールとして注目を集めています。しかし、生成AIをただの「文章作成マシン」として使うのではなく、地域性や文脈を反映させた形で活用するには、一定のスキルが求められます。そこで重要になるのが、「地域向けプロンプト」の設計です。
地域向けプロンプトとは何か?
プロンプトとは、AIに与える指示文のことです。その構成や文脈が明確であればあるほど、生成される文章は質の高いものになります。中でも「地域向けプロンプト」とは、地域の固有情報――地名、文化、歴史、対象読者など――を反映させた命令文を指します。たとえば「観光案内文を作ってください」ではなく、「長野県松本市の松本城を、修学旅行中の高校生向けに、歴史の魅力を伝えるような口調で紹介してください」と指示することで、ChatGPTはより具体的で読者に響く文章を生成します。このようなプロンプトは、単に情報を並べるだけではなく、誰に向けて、何を、どのように伝えるかといった文脈設計が重要です。
プロンプト構造の基本と応用
地域向けプロンプトを設計する際に押さえておきたい構造は以下の通りです:
「[地域名]の[イベント/名所/特産など]について、[対象読者]向けに、[目的]として伝える文章を[語調/トーン]で作成してください。」ここでポイントになるのは、対象読者と語調の指定です。例えば若年層にはカジュアルな語り口、高齢者には丁寧な文体、外国人観光客には簡潔で明快な表現が適しています。また、プロンプトには状況設定を付け加えることで、より洗練された文章を引き出せます。例えば「観光地を初めて訪れる人に向けて」「パンフレットの冒頭に掲載することを想定して」といった具合に、使用シーンを明確化することでAIの出力精度が向上します。
実践例:段階的プロンプトと会話型プロンプト
ChatGPTの特性を活かすなら、段階的に出力を深めていくプロンプト設計も有効です。たとえば:
- 「○○町の春祭りについて概要を紹介してください」
- 「その祭りに出る屋台について詳しく教えてください」
- 「祭りを地元の高校生が初めて訪れる体験談として書いてください」
こうしたプロンプトの連携は、ChatGPTをまるで取材先の案内人のように使う手法です。また、地域住民との架空対話を前提とした会話型プロンプトも有効で、以下のような使い方が可能です:
「あなたは○○町在住の70代の農家です。昔の○○祭りの様子を、孫に話すような口調で語ってください。」この形式は、地域の物語性や語りの雰囲気を引き出すのに効果的で、地域の温もりや人間味を含んだコンテンツづくりに役立ちます。
注意点:ステレオタイプと地域住民への配慮
生成AIは過去の言語パターンをもとに文章を生成するため、「のどかな田舎」「人情味あふれる地域」といったステレオタイプな表現を多用しがちです。こうした表現が実情と異なる場合、読者に誤った印象を与えかねません。また、地域の魅力を伝える際に、過度な演出や誇張が入ると、地元住民に違和感や反感を与える可能性があります。そのため、プロンプトには「誇張を避け、自然体で紹介してください」「地域の声を反映してください」といったバランス感覚ある指示文を添えることが重要です。
地域の物語を形にする道具としてのChatGPT
ChatGPTは、地域の価値を言葉にするための強力なツールですが、その力を引き出すには「何をどう語らせるか」という問いが欠かせません。地域向けプロンプトの設計は、単なるAI操作ではなく、地域の声を通訳し、外に届けるための編集行為とも言えるでしょう。プロンプトを通じてAIに語らせる地域の物語は、発信者の意図と地域への理解によって形作られます。言い換えれば、それは地域の未来像を誰かに届ける設計図なのです。
まとめ:地方創生におけるプロンプトの意味

この挿絵はGPT4oで作成
情報発信力の格差が、地域間の注目度や訪問者数に直結する時代において、生成AIの活用は小さな自治体にも大きな可能性を開きます。プロンプトという設計行為は、外部への“翻訳”であり、地域の内側の想いを丁寧に表現するための橋渡しです。地方創生の最前線でこそ、プロンプトスキルは必要とされています。ChatGPTが地域の物語を紡ぐための筆となるなら、その筆に何を描かせるかは、私たち自身の問いかけにかかっているのです。